今回は、児童指導員の皆さんに向けて、「安全な人間関係の距離感=バウンダリー(境界線)」をテーマにお話しします。
これは以前、当方の研修を受講した児童指導員さんからいただいた感想です。
施設の中で子どもと日々関わるということは、家族に極めて近い距離感で支援関係を継続するということでもあります。
特に、複雑な家庭環境で育ったり、虐待などの心の傷を抱えたりしている子どもたちと向き合うと、支援者自身の感情が大きく揺さぶられる場面も少なくありません。
一方で、児童指導員はあくまで「支援者」でありながら、子どもと家族的な親密さをもって関わることも求められます。
つまり、親密さと専門性のあいだで絶妙な距離を保ち続けるという、非常に高度な支援です。
その難しさを日々受け止めながら現場で子どもと向き合う——それは簡単なことではありません。
だからこそ、児童指導員にとってバウンダリー(境界線)の意識を持つことがとても重要です。
まずは、バウンダリーの基本的な考え方について、こちらのブログで確認してみてください。
上記のブログ記事では、バウンダリー(境界線)が保てない時に起きる問題を、「支配・被支配の関係」「共依存の関係」「無関心」という三つの関係性で説明しました。
それでは、安全な人間関係の距離感を保つために、どのような意識や気持ちで、利用者との距離を保つ必要があるでしょうか。ここから、チェックリストを紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
摩擦が生じやすくなる、子どもに対する考え方
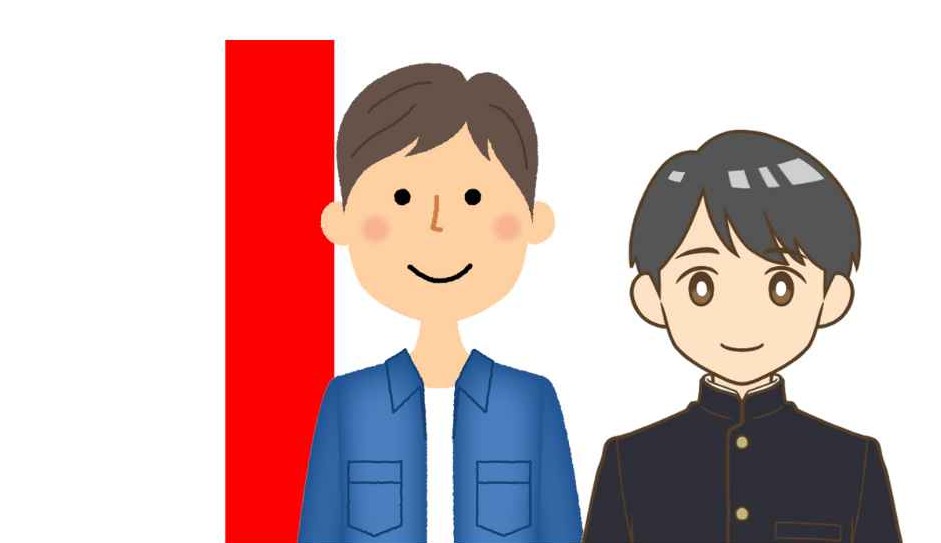
児童指導員の方々も、本当に熱心な方が多いですよね。
強い責任感や誠実さ、そして「何とかしてあげたい」という温かい思いがある。
その思いがあるからこそ、困難な子どもたちにも粘り強く寄り添い、信頼関係を築くことができます。
児童福祉の現場では、子どもから「家族のような存在」として見られることは多々あるでしょうし、支援する側もまた、家族のような立ち位置で関わらざるを得ない場面が多くあります。
だからこそ、支援者側の思いの強さは、より家族的で親密な関係を構築することにつながります。
気づかぬうちに、「職務としての支援」から「個人としての支え」へと境界が曖昧になり、仕事とプライベートの区別がつかなくなります。
子どもと安全な人間関係の距離感を保ちやすい考え方
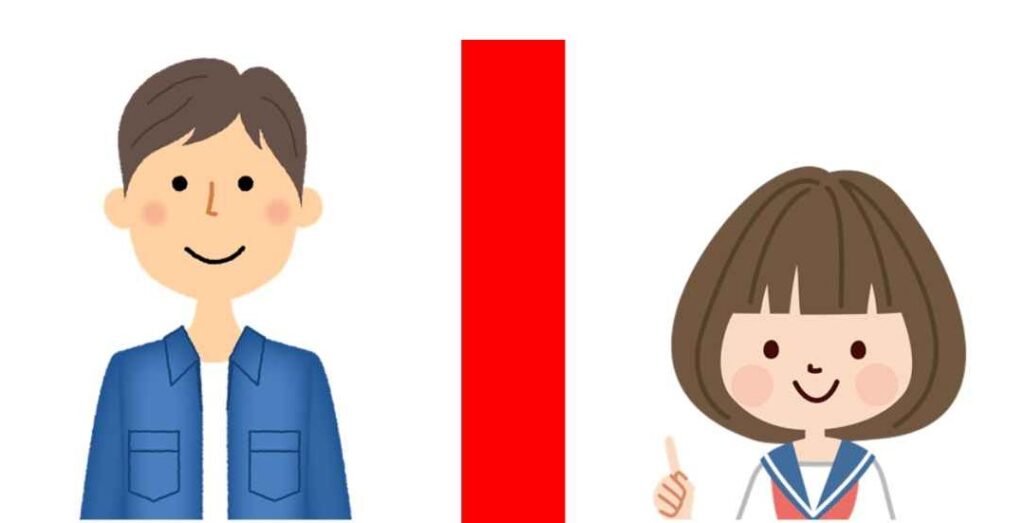
先ほどの「摩擦が生じやすい距離感」と比べると、こちらはずっと安全で安定した関わり方です。
仕事とプライベートの境界を意識することで、「子どもを守りながら、自分自身も守る距離感」を保つことができます。
思いの強さを持ちながらも、冷静さを失わず、支援者としての役割と責任に立ち戻れる考え方です。
児童指導員がコントロールを受けやすい、子どもの距離感
次は、子どもからの「児童指導員に対する思いの強さや考え方」がどのように関係性に影響を及ぼすのか、説明していきます。
当たり前のことですが、いくら児童指導員が距離の取り方に気を付けていても、子どもの距離感の影響は必ず受けてしまうものです。
「僕がこうなったの大人のせいでしょ?先生まで僕を見捨てるわけ?!」
このように要求が強いとコントロールを受けてしまうこともあるでしょう。

「気持ちに寄り添う」とは「要求に応えること」ではない。
子どもから暴言を受けたり、過剰な要求をされたりすることは、児童福祉の現場では珍しくありません。
そんな時、「なんとか落ち着かせなきゃ」「気持ちに寄り添ってあげたい」と思うのは自然なことです。
ただ、ここで押さえておきたいのは、「気持ちに寄り添うこと」と「要求にこたえること」は同じではない、という点です。
対人援助職の現場では、「気持ちに寄り添う」という言葉がよく使われます。
しかしこの言葉はとても抽象的で、誤解されやすい表現でもあります。
「寄り添わなきゃ」と思うあまり、相手の言動を受け入れすぎたり、無理な要求に応じてしまったりするケースも少なくありません。
その結果、支援者自身が疲弊し、子どもにとっても望ましくない関係が形成されてしまうことがあります。
子どもに「境界線を教える」ということは、人間関係には限界があることを教えることでもあります。
たとえ相手が傷ついた経験を持っていたとしても、「できること」と「できないこと」を明確に伝えることが大切です。
そして、「断ることは、あなたを拒絶しているわけではないんだよ」というメッセージをこめる。
これこそが、子どもにとって安全で信頼できる人間関係を学ぶ支援になります。
「主語を分ける」ことで、気持ちに寄り添いながら要求を断ることができる。

そうだね、つらかったよね。(私としては)その気持ちはわかるよ。でもね、この施設ではそれは認められていないんだ。わかってね。
相手を受け入れながら要求を断るときには、「私」と「施設」、そして「児童指導員としての立場」を分けて伝えることで、子どもとの関係を保ちやすくなります。
肯定的なメッセージを意識する。

先生としてできるのは、ここまでなんだよね。
「できないよ」ではなく、「できるのはここまでなんだよね」という伝え方も大切です。
虐待などの経験から、否定されることに敏感な子どもも多くいます。だからこそ、言葉の選び方ひとつで、安心感が大きく変わります。
たとえば

そうなんだ。今日は学校に行けなかったんだね。ゆっくり休めた?
このような言葉は、子どもの行動を責めるのではなく、その気持ちや状態を受け止めるメッセージになります。
「どうして休んだの!」といった否定的な言葉を日常的に浴びてきた子どもにとっては、こうした肯定的な関わりが「大人といても安心できる」と感じる、最初のきっかけになるのです。
児童指導員が共依存関係に陥りやすい、子どもの距離感
児童指導員が最も存在意義を感じる瞬間は、「子どもから必要とされている」と実感する時ではないでしょうか。
「先生が担当で良かった」と言われれば嬉しく感じるのは自然のことです。それ自体はノーマルなことですが、バウンダリー基礎講座でも説明した通り、感情の強さはバウンダリーにダイレクトに影響します。
その感情は、不安や怒りといったネガティブな感情だけではありません。嬉しい、喜び、安心といったポジティブな感情もまた、バウンダリーに影響を及ぼすため管理の意識が必要なのです。
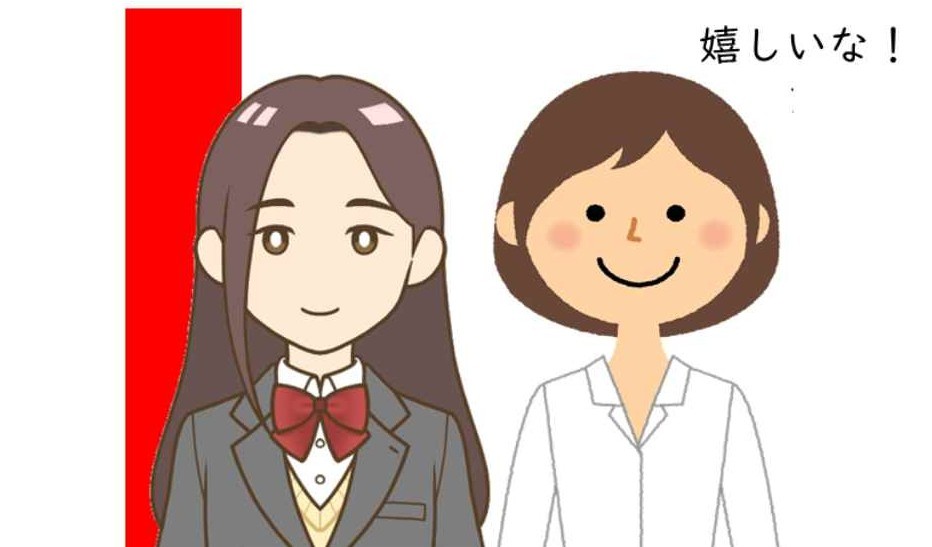
子どもの過剰適応を助長する児童指導員の「不安」
児童福祉の分野では、「過剰適応」の子どもへの対応がよく話題になります。
私がスクールカウンセラーを務めていた時も、教員からこのテーマで相談を受けることがありました。過剰適応の子どもは、大人の顔色を常にうかがい、大人が望んでいるだろう行動を素早く取ります。
たとえば、先生が困っていれば率先して挙手し、委員長などの役割を引き受けようとします。
こうした行動の背景には、「大人の不安や怒り」があります。
子どもは不安そうな大人を見ると、「私の出番だ」「これでほめてもらえる」「認めてもらえるかもしれない」と考え、過剰にがんばってしまうことがあります。
また、「怒り」も同様です。
イライラしている大人を見ると、子どもはその場の空気を敏感に察知し、すぐに機嫌を取ろうとします。
たとえば、片付けを率先して行ったり、怒っている相手の前で笑顔をつくったりして、緊張を和らげようとします。
一見「気が利く」「よく気づく子」と見えるかもしれませんが、その実、子どもは常に周囲の感情に合わせて自分を抑え、安心を保とうとしているのです。
児童指導員自身が不安や怒りなどの感情をうまくコントロールできないと、その揺らぎを子どもに敏感に読み取られ、結果的に過剰適応を助長する関わり方になってしまうことがあります。
だからこそ、児童指導員にとってネガティブな感情との付き合い方がとても大切です。
感情の扱い方については、以下のブログを参考にしてみてください。
大切なのは、バウンダリーを「保つこと」ではなく「意識すること」
ここまで読んでみて、いかがでしょうか。
バウンダリーの大切さは頭では理解していても、実際の現場でそれを行動に移すのは、決して簡単なことではありません。
また、今の子どもとの関係が「適切な距離を保てているかどうか」を判断するのも難しいものです。
でも、本当に大切なのは「バウンダリーを守ること」ではなく、「バウンダリーを意識する習慣を持つこと」です。
児童福祉の現場では、むしろ「家族的な距離感にならざるを得ない」場面の方が多いのではないでしょうか。
子どもたちは、生活のすべてを支援者の目の前で過ごしています。
だからこそ、単なる「支援者と利用者」という関係を超えた、深いかかわりになるのは自然なことです。
大切なのは、「いま自分は家族的な距離感で支援している」と自覚し、チームで共有しながら調整していくことです。
それができれば、子どもにとっても、児童指導員自身にとっても安全な支援関係を保つことができます。
常にバウンダリーの意識を持ち、点検する習慣をつくること。
そして、それを個人だけでなく、職場全体として取り組んでいくこと。
それが、児童指導員として長く健やかに支援を続けていくための大切な力になるはずです。
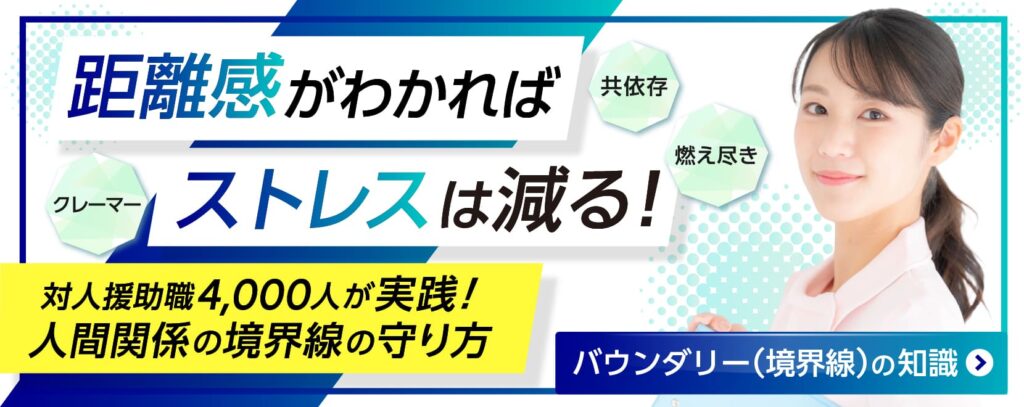
最新セミナー日程
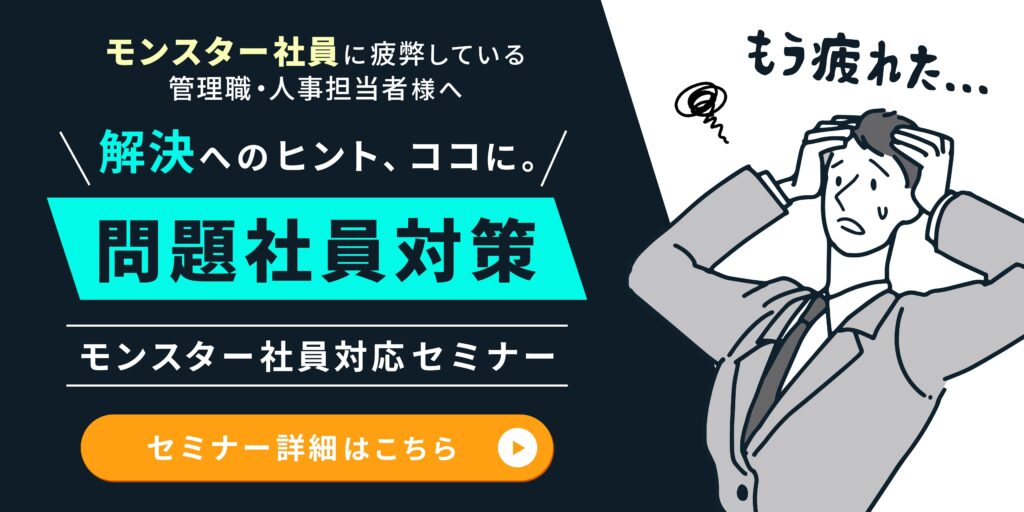
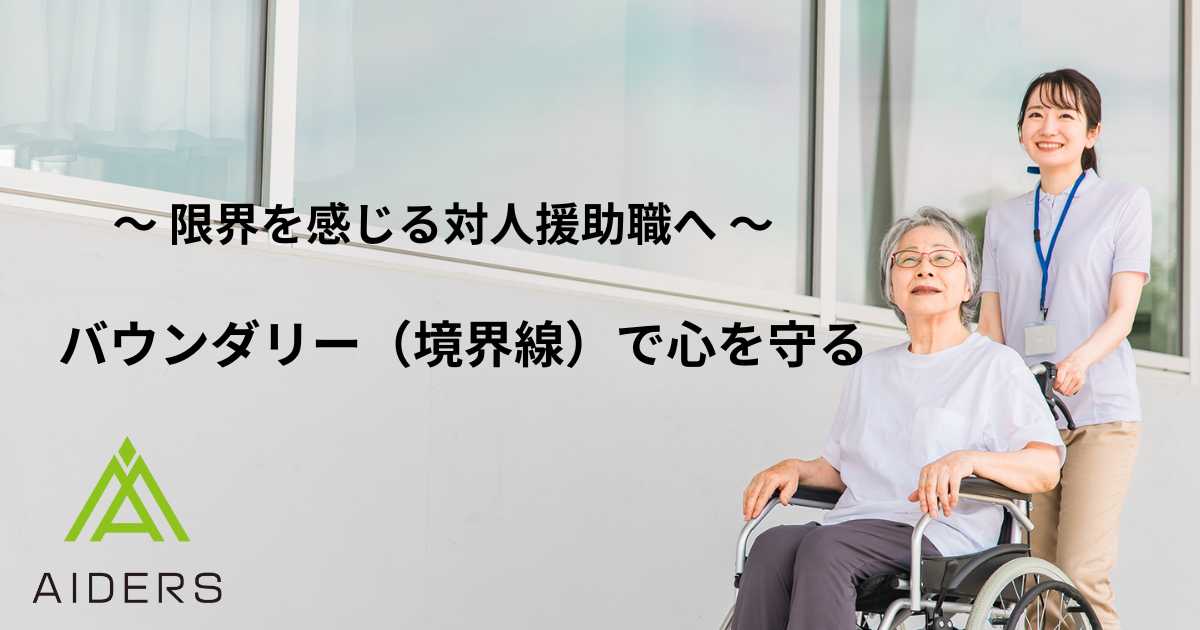

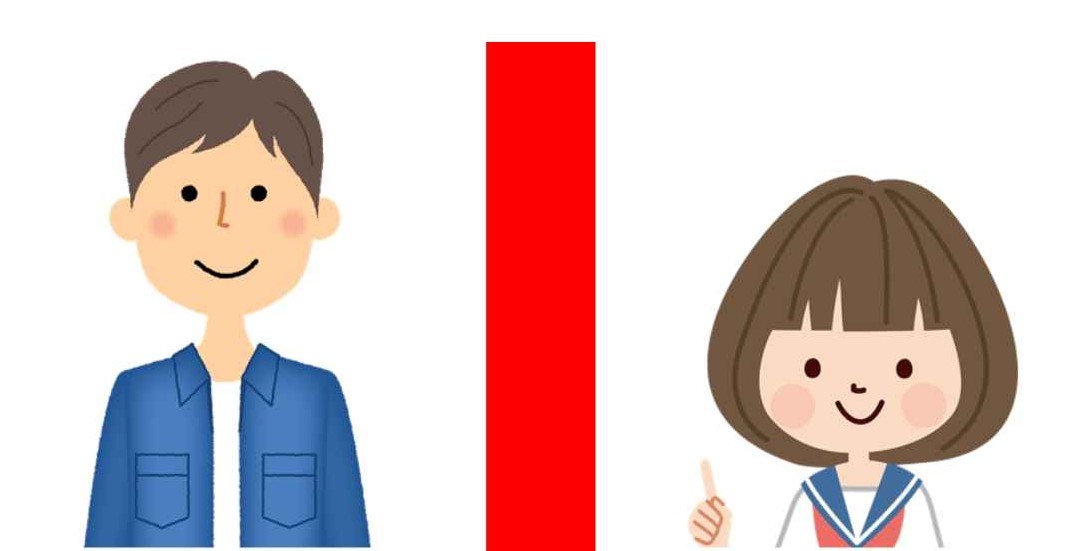
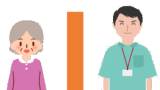





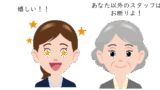





今回の境界線に関するセミナーは、心にグサグサと刺さるような内容ばかりであった。中でも特に印象に残っているのが、「『気持ちに寄り添うこと』と『要求にこたえること』は同じではない」という言葉である。
わたしが一年目の時は、「自分で子供の支援にかかわる仕事を選んだのだから、子供に何かされてもある程度は我慢しなきゃいけない」と強く思っていた。そのため、できるだけ子供の要望に応えることが子供の気持ちに寄り添うことだと思い、特に子供が怒っていたり不機嫌そうにしていたりする時には、これ以上子供が不穏にならないように自身の言葉や行動を選んでいたように思う。
今回のセミナーを通して「自分の感情を自分の責任として適切に扱うことが大切」ということを知り、自分が子供の感情の責任まで引き受けてしまったことに気づいた。その一方で、子供も適切な距離感を把握できていない場合があるため、まずは私たち職員が境界線を意識しながら子供と適切なかかわりを持つことが重要であると感じた。