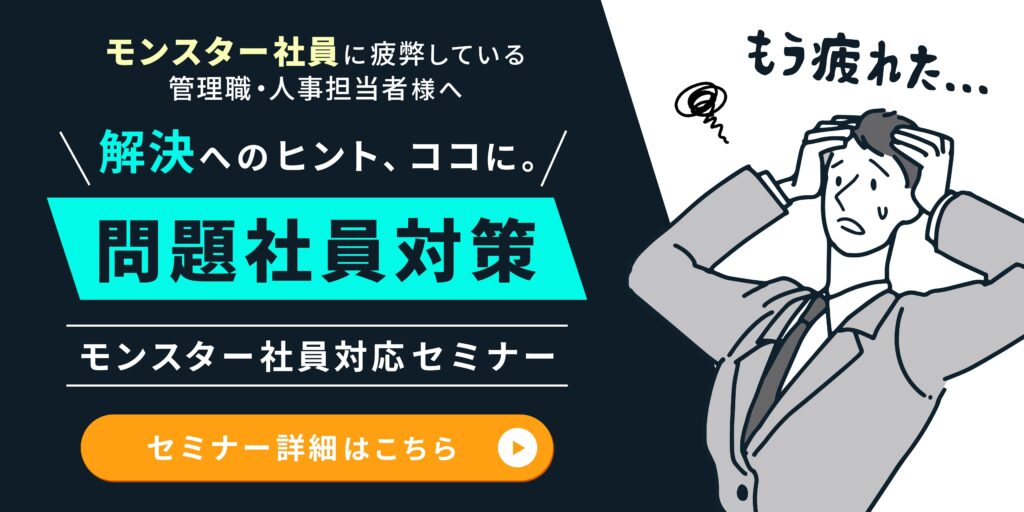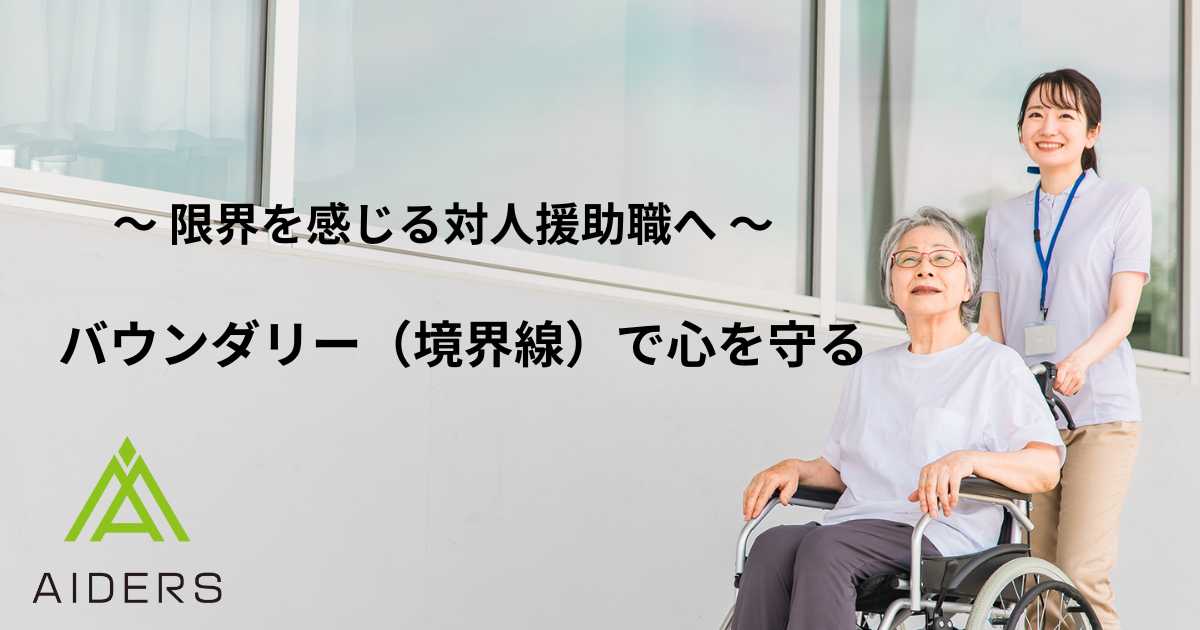うちに通っている男性利用者のセクハラ行為で困っています。
実際に、複数の職員が被害に遭っており、何度か注意はしているのですが、一向にやめてくれません。
職場としては、もう利用をお断りするしかないのではと思う反面、その方には精神障害があり、これまでずっと家に閉じこもっていた経緯があります。ようやく外に出て、うちの施設に通ってくれるようになり、他の利用者さんともだいぶ交流ができてきたところでした。
うちが断ることで、また家に引きこもってしまうのではないか……。そう考えると、彼の社会的な居場所を奪うことになりかねず、判断がとても難しいのです。
以前、ある介護事業者の団体で研修を行った際に、このようなご質問をいただきました。
これは、まさに対人援助職の現場におけるカスハラ対応の難しさを象徴するケースだと思います。
たとえば、一般の飲食店などであれば、悪質なクレームやハラスメントをする客は「出入り禁止」にして終わり、という判断が比較的しやすいですよね。
しかし、福祉や介護の現場では、話はそう単純ではありません。
その利用者を断るということは、社会的な居場所を奪ってしまうことにもなりかねません。
だからこそ、現場の管理職の方々は非常に難しい判断を迫られるのです。
「利用者のために、どの選択が正しいのか?」「私たちはどうすべきなのか?」
そう悩み、なかなか決断に踏み切れない。
これは、とてもよくあることですし、確かに簡単に割り切れる問題ではありません。
ただ、こうした問題に福祉職が向き合う際に、見落とされがちな重大なポイントがひとつあります。
それは、福祉職の“優しさ”がゆえに、「職場の安全衛生」という視点が抜け落ちてしまいやすい、ということです。
「ケース対応の問題」と「職場の安全衛生の問題」を分けて考えること
こうした悩みは、まさに対人援助職が日々向き合っている『ケース対応』の問題です。
支援者として、利用者に対してどう支援を継続できるかを模索する姿勢は、とても大切な視点だと思います。
こうした場合、関係者が集まりケースカンファレンスを行うなどして、対応されていますよね。
これが『ケース対応』です。
一方で、職場でセクハラが発生しているという事実そのものは、「ケース対応」の枠ではなく、『職場の安全衛生の問題』として捉えなければならないのです。
対人援助職の現場では、どうしてもこの視点が弱くなりがちですが、忘れてはならないのが、職場には「安全配慮義務」があるということです。
事業主は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をするものとする。(労働契約法第5条)
事業者(法人・管理職)には、従業員の生命と心身の健康を守る法的な義務があります。
たとえば、セクハラを放置した結果、被害を受けた職員がうつ病を発症し休職した場合、これは「安全配慮義務違反」として、労災認定や損害賠償請求の対象となる可能性があります。
精神障害の労災申請は「医療・福祉」が最多
厚生労働省の最新データによると、精神障害による労災申請は「医療・福祉」業界が最も多く、支給決定件数もトップです。
出来事別に見ると、ハラスメント被害(パワハラ・カスハラ・セクハラ)が上位を占めており、福祉現場は特にリスクが高いことがわかります。
利用者支援を優先するあまり、職員の安全衛生を軽視すると、深刻な労災につながる可能性があります。
福祉現場では、職員の安全も支援の大切な一部。
当たり前のことですが、「職場の安全」が確保されてこそ、初めて「質の高い利用者支援」が実現できるものだと考えています。
もし、利用者支援を優先するあまり、職場の安全衛生を軽視してしまえば、それは本末転倒です。
スタッフがセクハラ被害を受け、疲弊し、休職や退職が相次げば、人手不足となり、結果として利用者の居場所さえ守れなくなるかもしれません。
だからこそ、「支援」と「安全」はどちらかを選ぶものではなく、両立させなければならない課題なのです。
利用者の居場所を守りたい気持ちは大切にしてほしいのですが、管理職は常に「職場の安全衛生」の意識を持って、検討をしていく必要があります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※職場の安全衛生については以下の記事もぜひ読んでみてください。
最新セミナー日程