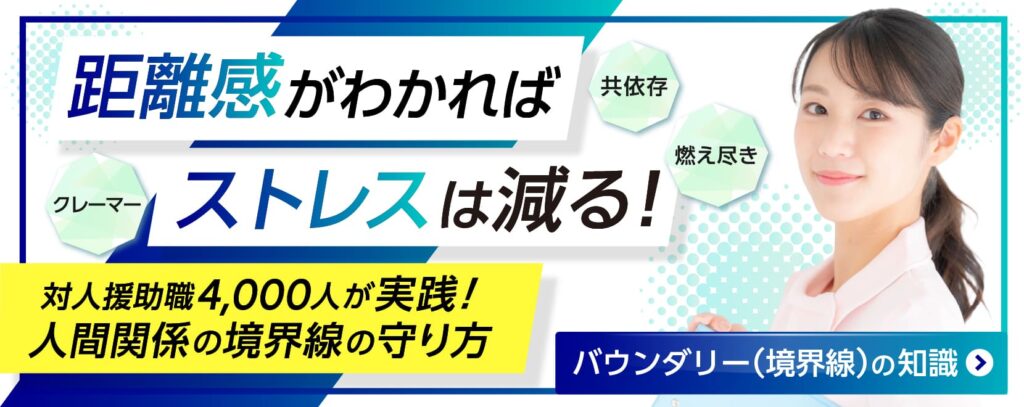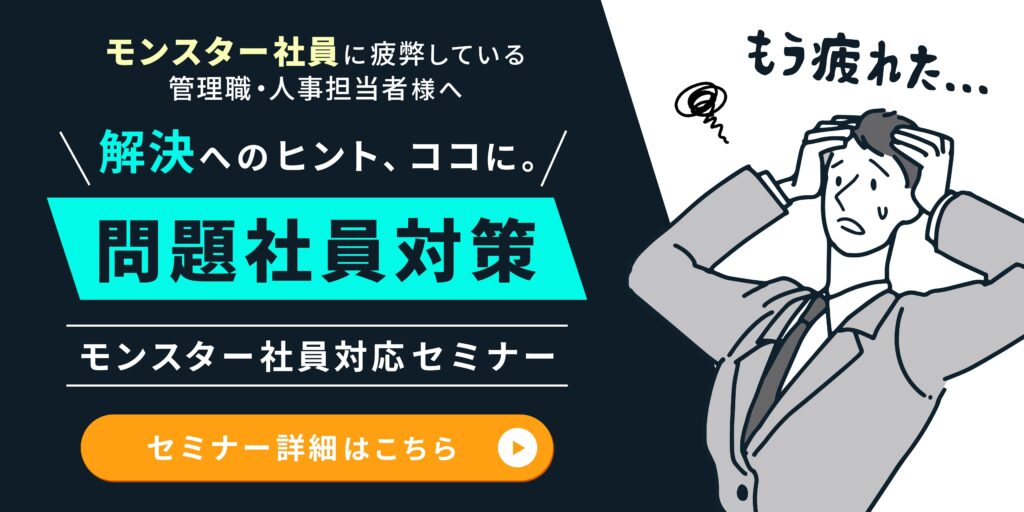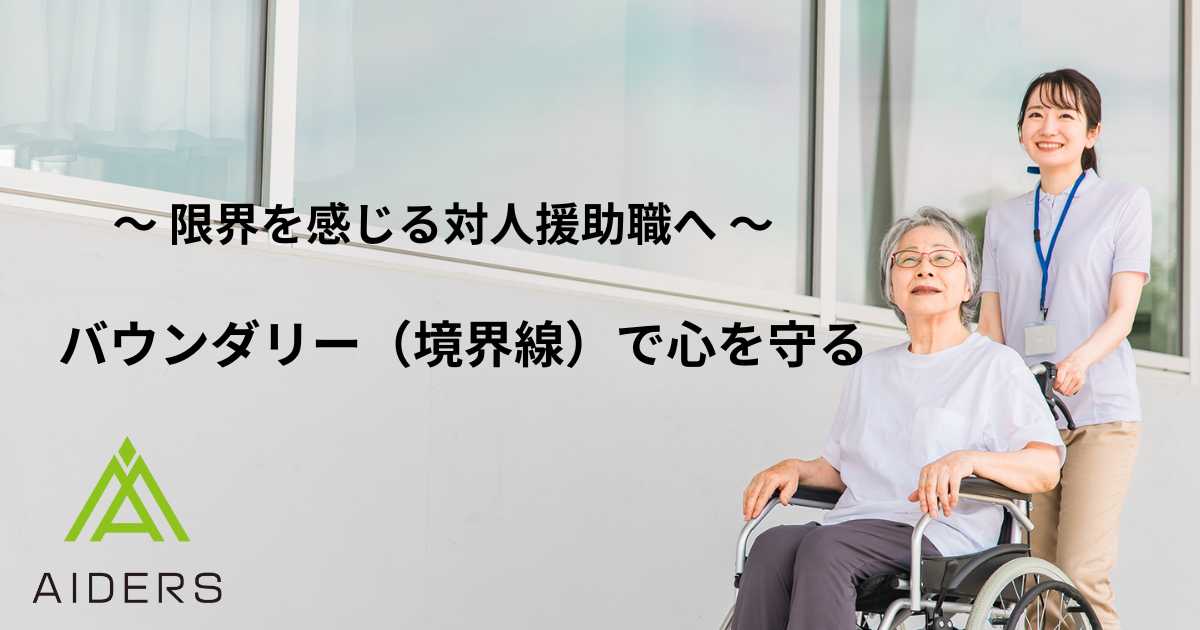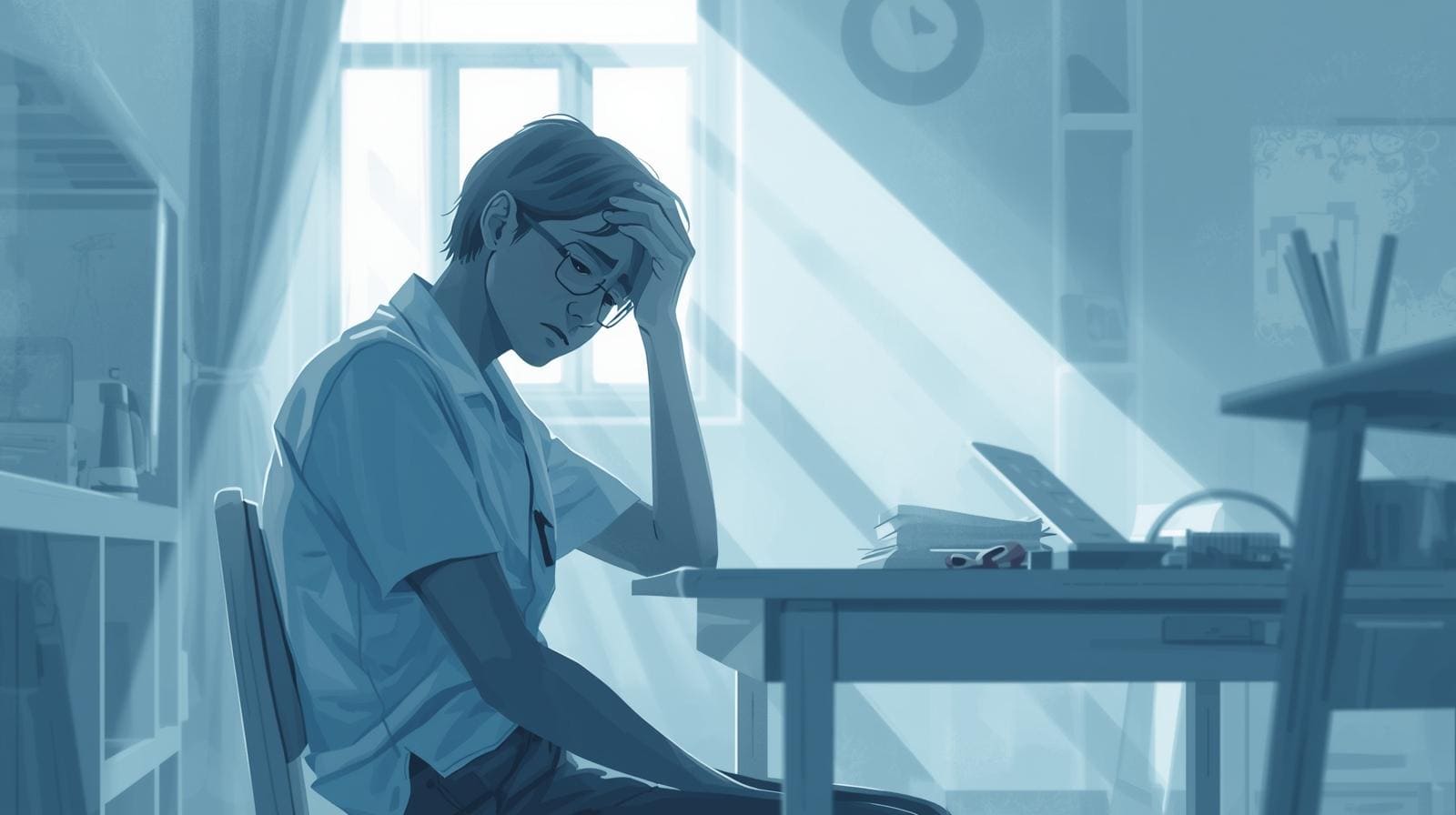仕事に行くのもつらい…そんな気持ちを抱えながら、今日も職場に向かっている児童指導員のあなたへ。
「子どもたちの姿に、自分の過去のつらい記憶が重なり、フラッシュバックのように思い出が押し寄せて苦しくなる」
このようなお悩みを、児童指導員や保育士の方から聞くことは少なくありません。
体調もすぐれない状態で働いているため、子どもたちに対してイライラしてしまう自分に自己嫌悪を感じることもあるでしょう。
まず、実際に寄せられたお悩みを紹介いたします。
過去の傷がよみがえり、仕事に行くのもつらい…

児童養護施設で児童指導員1年目として働いています。
僕は両親が小学生の時に離婚しているんですが、離婚の原因は父から母への暴力でした。父はお酒を飲んでは暴れて、母を怒鳴り、殴ったり物を投げたりして大変だったんです。僕も何度か殴られたり、投げられたりしたことがありました。
母がいつも泣いていたこと、あと、僕が毎日父に怯えて過ごしていたことは今でもはっきり覚えています。
児童指導員になったのは、自分と同じように苦しい思いをしている子どもの力になりたいと思ったのがきっかけです。
新卒で今の職場に入れたのは良かったのですが…。子どもたちと日々接していく中で、過去の記憶が生々しく出てくるようになってしまいました。
特に自分と同じように虐待を受けていた子どもを見ていると、本当に苦しくて。仕事中に動悸が激しくなって、とても苦しくて、この間はトイレに駆けこんで休みました。
仕事に行こうとすると吐き気がして、毎日本当に苦しい思いで出勤しています。家で泣いてしまうこともありました。
とても辛いし、この仕事は続けられないのではないか?と思うのですが…。でも、なんとか続けたいです。
こんなことで逃げていたら、どんな仕事も務まらないのではないかと思いますし、トラウマも克服しないといけません。
なんとか良くなる方法を探しています…。
とても辛く苦しいお悩みです。
職場で過去の体験がフラッシュバックされるというのは、言うまでもなく大変なことです。
仕事が苦しいのはもちろんのこと、フラッシュバックが続くとなると毎日を生ききることが本当に苦しい状況でしょう。
本当に頑張っていらっしゃると思います。
ここからあなたがどのようにこの問題に対処していくのか、ブログの範囲で説明できることを書いていきます。
ぜひ最後まで読んでみてください。
トラウマと付き合うために知ってほしいこと。
専門家に相談する。
まず大前提としてですが、あなたが自身の体調不良の原因について「もしかしたらトラウマが関係しているのかもしれない」と気づけていることは、とても大切で素晴らしいことです。
というのも、トラウマに気づかずに「なぜか職場で動悸が止まらない」「仕事に行こうとすると吐き気がする」といった症状に悩まされている人も少なくありません。
原因がわからずに苦しむよりも、「これは過去の体験と関係しているのかもしれない」と自覚できていることは、大きな一歩なのです。
そのうえで大切なのは、一人で抱え込まず、専門家に相談することです。
現在の症状がどの程度深刻なのか、今の状態で仕事を続けてもよいのか。
これは自己判断ではなく、専門家と一緒に確認する必要があります。
安全を確保しなければ向き合えないトラウマもある。
ここで知っておいていただきたいのは、トラウマには「安全が確保されなければ向き合えないものもある」ということです。
- トラウマの深刻度によっては、あえて今は詳しく触れずに生活の安定を優先した方がよい場合があります。
- 職場でフラッシュバックが繰り返し起きてしまうと、その状態で無理に過去と向き合おうとすることで、かえって状態が悪化することもあります。
- 深刻なトラウマと向き合うには多くのエネルギーを使うため、「安心して休める環境」や「支えてくれる人とのつながり」が必要です。
だからこそ、自己判断はリスクが高いのです。
「今の状態で働き続けられるのか」「休養が必要なのか」など、あなたひとりでは判断できません。
まずは専門家に見極めてもらうことが、安心して回復に向かう第一歩になります。

精神科とカウンセリングの違い。
「相談したいけど、どこに行けばいいのかわからない…」
そう感じる方も多いと思います。
大きく分けると、相談先は 精神科(または心療内科) と カウンセリング の2つです。
- 精神科・心療内科
診断や薬の処方を通して、医学的にサポートしてくれる場です。
「今の状態で仕事を続けられるのか」「休職が必要なのか」といった就労可否を判断してもらうこともできます。
必要に応じて診断書を出してもらえる点も重要です。
診察時間は初診で30分~60分、再診では10分前後が一般的ですので、「じっくりと話を聞いてほしい」「過去の体験を一緒に振り返ってほしい」といったニーズがある場合は、カウンセリングも併用することをお勧めします。
- カウンセリング
うつ病を例にすると、医師は「診断をして薬を出す」役割を担います。
それに対してカウンセリングは、「なぜうつ病になったのか、その背景や原因を一緒に整理し、改善に向けてどんなことができるのかを一緒に考えていく」役割を持っています。
トラウマの問題についても同じです。
安心できる場で、過去の体験を少しずつ確認しながら、今後の取り組み方や自分に合った対応を一緒に考えていくことができます。
また、カウンセリングは精神科よりもハードルが低く感じる方が多いため、「精神科を受診すべきか悩んでいる」といった相談も多く寄せられます。
カウンセリングについては以下のブログ記事でも詳しく説明しています。
ここまでご確認いただいたように、専門家への相談はとても大切ですが、職場への相談も欠かせません。
まずは上司や信頼できる先輩、そして産業医がいれば産業医に相談してみてください。
あなたの状態を職場が理解していることで、業務負荷を軽減してもらえたり、配慮を受けながら働けたりする可能性があります。
「迷惑をかけてしまうのでは…」と感じてしまう方も多いですが、状態を隠して無理を続けることの方が結果的に大きな負担となります。
どうかサポートを受けながら、安心して続けられる環境を整えていってくださいね。
「克服」についてのよくある誤解。

なんとか良くなりたいんですよ。
だから、苦手な状況から逃げてはいけないと思うんです。
フラッシュバックが怖いからって職場から逃げるのではなくて、職場に行っても大丈夫なようにならないといけません。
だから、なんとか克服したいんです。
「なんとか良くなりたい」と思う気持ちは、とても自然です。
でもこれは、よくある誤解です。
トラウマがある方の多くは、「あえて危険な場所に近づいて自分が大丈夫であることを確認したい」という傾向があります。
しかし、危険な場所に無理に近づく必要はありません。
フラッシュバックや強い反応が出ることは、極めて自然なことです。
反応が起きる自分を責める必要も、恥じる必要もありません。
大切なのは、
- どの場所や状況なら健康に影響が出ずに安全なのか
- どの程度なら自分が耐えられるのか
- どんな生活を自分が望んでいるのか
などを、時間をかけて慎重に整理していくことです。
トラウマはすぐに解決するものではありません。また、解決の方法や在り方は人それぞれです。
焦らず、自分のペースで向き合っていけば大丈夫です。
フラッシュバックに「上手に付き合う」
そんなふうに感じてしまう方はとても多いです。
でも実際には、フラッシュバックが起きることは悪いことではありません。
それはあなたの体と心が、危険を察知して自分を守ろうとしている自然な反応です。
トラウマ反応をなくすことを目指すのではなく、「反応が起きてもダメージを少なく済ませて、元の状態に戻ってこれること」を目指していく。
これが「トラウマと上手に付き合う」という考え方です。
簡単に下の図で説明します。

感情の波は誰にでもありますよね。黄色のゾーンでおさまっている間は、「安全ゾーン」です。
赤のゾーンが「大ピンチゾーン」です。(名前はなんでもいいです。自分でつけてください)
フラッシュバックが起きている時がまさにそれでしょう。
「戦場に引きずり込まれる」と表現したクライエントさんもいました。
ここで耐えがたい苦痛を味わい、大きく取り乱してしまうのです。
トラウマと付き合う、というのは
- 赤のゾーンの時、心や体にどんな反応が起きるのか。
- どれくらいの時間で元に戻るのか
- どのように過ごすことで「まだマシな状態」にいられるのか
こうしたことを整理し、「始まりから終わりまでの見通し」を立てていくことです。
赤のゾーンの強烈な苦痛の記憶だけでなく、波がおさまっていく時のことまで、ちゃんと覚えておく。
それを数稽古のように繰り返すことで、少しずつ「戻ってこられる力」が育っていきます。
「トラウマの克服」を生きる目的にしてはいけない。
こうして「感情の波を理解し、少しずつ付き合い方を学んでいく」ことが大切になります。
ただ、ここで意識してほしいことがあります。
それは、「トラウマを克服すること」そのものを生きる目的にしてしまわないことです。
これまで、カウンセリングの場面で非常に多くのトラウマ相談を受けてきました。
その中で最近気になっているのは、「トラウマを克服することだけに目が向いてしまい、それそのものが生きる目的になってしまっている人」が多いことです。
- フラッシュバックが出るたびに「全然良くなっていない!」「これまで受けた治療はすべて無意味だった!」と自暴自棄になってしまう。
- 良いと思う治療法を片っ端から試してみるけれど、なかなか安心できない。
- 余暇の時間もトラウマの本などを読み漁ってしまい、リラックスした別の過ごし方ができない。
- いくつものカウンセリングや医療機関を渡り歩きながら、どうしても焦ってしまう。
これらの行動を「間違っている」と言いたいわけではありません。
むしろ、少しでも楽になりたい、安心したいという切実な気持ちの表れだと思います。
ただ、克服そのものを人生の目的にしてしまうと、生活の軸が定まらずに混迷し、余計に不安定になってしまうこともあるのです。
大切なのは、トラウマをなくすのではなく、理解して賢く付き合うことです。
克服に人生をささげず、あなた自身の人生を楽しむこと。
カウンセリングでも支援できますので、辛さを抱えたまま一人で悩まずに安心してご相談ください。